虚数や複素数の存在に納得する、もう一つの説明
数学ブログ、お久しぶりの記事です。
最近はプログラマ界隈でも数学の話題が多くなってきて嬉しいです。
ここ最近ネットウォッチしていると、複素数について初心者にその意義を語る記事やプレゼンテーションを多く見かけます。そこでされている説明は、有名な「オイラーの公式」を出して美しいと説きつつ計算の簡便化につながるという流れが多いように感じます。
確かにそれも大事なのですが、今回は複素数が数学にとって必要だと、私が数学を学んで感じたことを書こうと思います。
高等数学(大学以降の数学)の定理や内容に言及することがありますが、高校数学でだいたい分かる内容です。専門過程で高等数学を学んだ方は用語や議論が曖昧であるという印象をいだくかもしれませんが、わかりやすさを優先した結果だと思ってください。
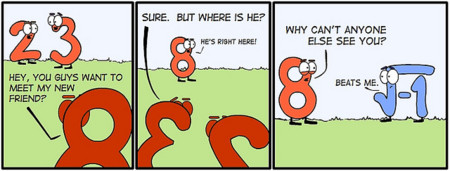
虚数と複素数について
虚数(または虚数単位) $i$ とは2乗して$-1$になる数と定義します。
\[ i^2 = -1 \]
この $i$ は $\sqrt{-1}$ とされることもありますが、平方根の定義が「2乗してそれになる数」なので、もう少し正しく書けば $\sqrt{-1} = \pm i$ です。このあたりは高校生が混乱するところですね。
ちょっと考えると「$i$ と $-i$ って役割一緒じゃない?」と思いますが、数学的には同型という概念で捉えられていて、言葉が妙ではありますが $i$ の定義と $-i$ の定義を入れ替えても同じことですし、2つはある意味同じ役割です。共役複素数という言葉はこのあたりの雰囲気がわかっていると理解しやすいです。
$a$ と $b$ を実数とすると、この虚数を使った $z = a + bi$ のことを複素数といいます。
ちなみに、虚数の「虚」は「うつろ」という意味で「嘘」という意味とは異なります。英語では「想像上の数」といった直訳が相当な imaginary number という単語で書かれます。
数学の歴史は方程式を解く歴史
数学には幾何学であるとか代数学であるとか色々なジャンルがありますが、一つの潮流として、数学の歴史は方程式を解く歴史だったと言えます。数の概念が拡張されるのも、大体は方程式を解くためだったのです。より厳密に言えば「代数方程式」と呼ばれる、変数のべき乗だけを使った方程式です。
自然数から有理数の誕生
ギリシア時代、大昔の人が存在を疑わないのは物を数える数である「自然数」、いわゆる $\mathbb{N}=\{1,2,3,4,...\}$ のみでした。
例えば1次方程式
\[ 3x + 2 = 8 \]
は $x = 2$ を解に持ちます。しかし
\[ 3x + 4 = 8 \]
は $x = \frac{4}{3}$ という有理数の解を持ちます。本来は「比がある数」なので、有理数ではなく有比数と訳したほうがわかりやすかったかもしれませんね。英語では比の意味である ratio から派生した rational が有理数を意味します。
正の有理数の誕生です。
当時は円周率 $\pi$ であったり三角関数の有名角の値は近似値で扱われていたので、無理数の発見はまだ先になります。
線分の長さを扱う三角測量だったり天文学が発達していたことからも分かる通り、正の有理数は大昔から普通に受け入れられいたようです。
無理数の発見
そんな中で三平方の定理とも呼ばれるピタゴラスの定理で有名なピタゴラスは、ピタゴラスの定理から、1辺の長さが1の正方形の対角線の長さが $\sqrt{2}$ であることを発見し、これが有理数でないことを見出します。
\[ x^2 = 2 \]
の解として現れることはご想像の通りです。
しかしピタゴラス学派は線分を極小の点の有限個の集合だという立場を取っていて無理数の存在を否定していたため、これは大きな事件となります。
$\sqrt{2}$ が無理数であるという証明は、背理法を使ってできます。
もし $\sqrt{2}$ が有理数であれば、互いに素 (割り切る数がない) である2つの自然数 $n$ と $m $ があって、
\[ \sqrt{2} = \frac{n}{m} \]
と表すことができます。しかし
\[ 2 = \frac{n^2}{m^2} \]
であるものの、$n$ と $m $ が互いに素なので $n^2$ と $m^2$ も互いに素であり、この式は矛盾となります。$m=1$ の場合には $\sqrt{2}$ が自然数ということになりますが、2乗して2になる自然数がないことは明らかで、この場合も矛盾となります■
無理数もまた「無比数」と訳されたほうが良かったかもしれませんね。何かが無理という意味でもないので。
無理数が人々に「数」として理解されるには、また時間がかかるのでした。
0と負数の発見
今では誰もが普通に扱っている0や負数(マイナスの数)も、最初の発見は7世紀のインドを待つ必要があります。
それでもヨーロッパでは、17世紀頃まで負数の扱いについては混乱があったというのですから、「新しい数」が受け入れられることは大変なのだと感じます。
中学校の教育課程で「マイナスの数をどう教えるか」ということはたびたび問題になります。その多くは方角であるとか借金であるとか、向きのある数として教えるということに帰着しているようですが、これは1次元ベクトル的な考えですね。
掛け算(乗法)の逆元である逆数は小学校で習うのに、足し算(加法)の逆元である負数は中学校で習うことからも、負数は正の数の分数より抽象的なのかもしれません。また、負の数が見出されるからこそ 0 という数も見えてくるのだと言えましょう。
現代では誰もが当たり前の存在だと思っているマイナスの数でさえ、ほんの数百年前までは誰もが理解できるものではなかったのです。
これにより、今まで負数になって解なしとされてきた方程式にも解が与えられることになります。
\[ x + 5 = 2 \]
の解は $x = -3$ と表されることになりました。
このあたりから左右に無限に伸びる数直線と実数というものが見えてきます。
見え隠れする複素数
「数の歴史は方程式を解く歴史」であることを考えると、誰もが考えるのは、それに沿えば解が求められる「$n$次方程式の解の公式」ということになります。
中学校でも習う2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$ の解の公式は、昔からよく知られていました。
\[ x = \frac{ -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} }{ 2a } \]
上記で平方根の中にある $D = b^2 - 4ac$ を「判別式」と呼んで、$y = ax^2 + bx + c$ の二次関数のグラフの $x$ 軸との交点の数を判別する式であることもまた有名です。複素数、二乗して$-1$になるような数の存在を否定するのであれば、$D$ が負の場合「解が無い」といえばいいだけです。昔はそういう態度をとってきました。
しかし、16世紀に3次方程式の解の公式が追求され、その中でイタリアの数学者カルダノが示したのが(実際の発見者は別の人でしたが)虚数を使った3次方程式の解の公式でした。しかしカルダノによる方法では、たとえ実数しか解がない3次方程式でも負の平方根を取る必要があり、このあたりから方程式を解くための複素数というものが見え隠れしてきます。
この分野はさらに発展していき、5次以上の方程式(代数方程式)には解の公式による解の表現ができない(ガロア理論)という発見など、近代の方程式論に進んでいきます。
代数的数が全てなのか
有理数を係数に持った $n$次方程式(有理係数$n$次方程式)を考えます。
\[ a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0) \]
ここで係数 $a_n, \dots a_0$ は有理数です。
この方程式が出す解を考えてみます。
簡単な2次方程式や3次方程式を想像すると、平方根だったり立方根だったりはすぐに出てきます。簡単に想像すれば、任意の有理数と累乗根を加減乗除で組み合わせたものが解になるんじゃないかと思えますし、それでだいたいあっています。
この有理係数$n$次方程式の解のことを「代数的数」と呼ぶことにしましょう。この中には虚数 $i$ が入っていることとします。はたして代数的数以外の数はあるのでしょうか。それには18世紀の数学者の成果を待つ必要がありましたが、結果的に代数的数ではない数が多数存在することがあることがわかりました。この数のことを超越数と呼びます。例えば円周率 $\pi$ は超越数である、つまり代数方程式の解とならないことがリンデマンという数学者によって証明されました。
虚数単位 $i$ を使わない代数的数、それが数直線全体ではなく、さらに多くの数があったのです。超越数も入れた「数直線全体」のことを実数 $\mathbb{R}$ といい、実数 $a$ と $b$ によって $z = a + bi$ と書かれるものを複素数といいます。
超越数の存在自体は代数方程式とは別の興味からの登場でしたが、それは微分積分学などでは欠かせないものでした。
ここで現代の我々が必要とする、実数、そして複素数という数が登場することになりました。
複素数の浸透とガウスによる代数学の基本定理
18世紀から時代を少し戻します。
16世紀にはまだ奇妙な数として避けられてきた複素数も、18世紀のヨーロッパの数学者の間では数学の発展に欠かせない道具として扱われるようになりました。その数が存在するかしないかという議論以前に、複素数を避けた議論では実りのある数学ができなかったのです。
16世紀までの流れで発見されたのは、虚数 $i$ も含む「代数的な数」です。
有名な数学者ガウスは $n$次方程式を研究し「代数学の基本定理」と呼ばれる以下の定理を証明しました。
「複素係数$n$次方程式は重複を含めて$n$個の解を持つ」
中学数学でも触れられますが、重複というのは2次方程式でいう $(x - 1)^2 = 0$ のような場合です。この例の場合、$x =1$ はこの方程式の(2次の)重複解である、または重解であるといいます。
証明は、任意の複素係数$n$次方程式 $f(z)$ が $(z - a)$ という因数で因数分解できることが言えれば、片割れは $n-1$ 次方程式なので帰納的に証明できます。ただ、これは初等中等的な数学では難しいので省略します。
この代数学の基本定理は、$n$ という数字が韻を踏んでいるというだけでなく、複素数全体が代数方程式の係数としてそれで十分であることを言っています。つまり
- 「有理係数$n$次方程式」→ 解に$i$が出てくることがある
- 「実係数$n$次方程式」→ やっぱり解に$i$が出てくることがある
- 「複素係数$n$次方程式」→ 解は複素数の範囲におさまっている
これは $n$ がどんなに大きな数でもです。$n$ が 1 から 2 になり、そして 3 になって避けがたくなってきた複素数。避けることで実りを失うよりも、これを受け入れさえすれば、もうこれ以上数の概念を広げなくてもいいのです。これってすごいことだと思いませんか?
この複素数が代数方程式の範囲内である意味十分な数であることを「複素数は代数的閉体である」といいます。
複素数が持つ大事な性質の一つ、それは代数的閉体であることでしょう。
解の公式であるとか興味は尽きることはありませんが、代数学の基本定理と複素数が代数的閉体であること、これらは代数方程式の研究の一つの到達点といえましょう。
実数の連続性と微分積分学
ここで代数方程式から離れて、超越数全体を加えた実数と微分積分学について考えてみます。
超越数の発見で、実数全体というものは当初考えていた代数的数よりもさらに凝縮された濃い世界であることがわかりました。
無限を数のように比較することを初めて厳密に行ったカントールという数学者の手法でも、代数的数全体よりも超越数を加えた実数全体のほうがはるかに「大きい」ことがわかりました。我々が代数方程式から導き出せない数は大量にあったのです。
有理数、または代数的数全体の集合で数列を作った際、その極限値として超越数が現れることがありますが、超越数全体を加えた実数全体では、その極限値も実数であることが保証されます。このような実数の集合の性質のことを「完備距離空間」であるといいます。
微分積分を運用する上で、完備距離空間という性質は避けては通れません。実数は微分積分にとって必要不可欠な集合だったのです。
では、微分積分学にとっての複素数とはなんでしょうか。複素数も実数から完備距離空間の性質を受け継いでいます。つまり複素数の点列の極限も必ず複素数になります。
実数関数の微分積分学をやっていても、そこから複素数が発生することはありませんでした。しかし、複素数関数の微分積分学は、概念の一つ一つが実数のものより強力で、そこから多くのことが見えてくることがわかったのです。
実数では、微分できることの条件は比較的緩く、その代わり微分した関数が更に微分できるかといったことはケースバイケースでした。それは高校数学の微分積分で習うような「左側微分係数」であるとか「右側微分係数」であるという概念が分かりやすい要因となっています。左側微分係数がない関数を不定積分した関数を提示すれば、一度は微分できるけれど、二度目はその点での微分はできない(左側微分係数がない)ということが起こり得ます。
しかし複素数では、微分に使われる極限の概念が左側とか右側というものではなく、複素数を平面に見立てた複素数平面の点として全方位からの極限という非常に厳しい条件となります。この厳しい条件の極限において定義域全部で一回微分できる関数は、なんと何回でも微分できることになるのです。これは実数関数には無い複素関数の非常に強力な性質となります。また、実数で扱いに困る $+\infty$ と $-\infty$ という「2つの無限大」を、複素数では一つにまとめて扱うことができ、複素数全体を球面に投影して議論することも可能になりました(実数の微分積分学では右側極限と左側極限を分けているなどの理由で、そのままでは実数軸を輪っかにして議論することはできないはずです)。
この微分が実数関数以上に強力な性質を持つことで、実数の微分積分学では見えなかったことが次々と分かるようになりました。実際にはベクトル解析という分野において同等の計算をすることもできますが、複素数の微分積分学のほうが多くの場合で事実を完結に導くことができ、複素数の微分積分学は前述の複素係数の代数方程式に重要な結果も簡単に導くことができる有用なものでした。
複素解析や複素関数論と呼ばれる複素数の微分積分学において、複素数とは実数から引き継いだ「完備距離空間」であるという性質と、その極限概念が持つ強力さが導き出す様々な性質、そして実数で扱いづらい2つの無限大を統一して扱うことができることにメリットがあります。
数学に詳しい方は、複素平面 $\mathbb{C}$ に $\{\infty\}$ を合併した空間がリーマン球面に同型であり、それが完備距離空間よりリーマン球面上で点列コンパクトであるので、コンパクト空間が持っている良い性質を $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ が備えているという理解でも大丈夫なはずです。
複素数の重要な性質のまとめ
今まで出てきた複素数の重要な性質をまとめてみましょう
- 代数学(方程式を解く)という研究からは、「複素数が代数的閉体である」という性質
- 解析学(微分積分をする)という研究からは、「極限と微分が持つ意味が強力であり、そこから有用な定理が導き出せる」ことと、「複素数に一つの無限大を付けた空間が完備距離空間である」という性質
特に代数的閉体であるという性質は、代数方程式を解くために生きてきた我々がこれ以上そのために数の概念を広げなくてもよいという、一つのゴールに到達できたというふうに思えます。
また代数方程式より出てきた虚数というものを微分積分学に導入すると、今まで扱いが面倒だったものの内なる性質が次々と見えてきて、代数方程式が要求する定理などの証明も簡単になるのでした。
多くの方が感動するオイラーの定理(指数関数と三角関数は複素関数として簡単な関係で結ばれる)は、この微分積分学のほうの成果の一つでした。しかしオイラーの時代の牧歌的な導入方法以上にきちんとこれを正当化するには、解析接続であるとか複素関数論の議論がもう少しだけ必要になります。
複素関数論においては複素数は計算道具っぽく扱われることも多く、実際にオイラーの定理などは実数の世界で生活していた我々に与えられた便利で強力な複素関数の道具であるという側面が大きいのですが(三角関数の公式とか高校生のように覚えなくなります)、重要なのは実数上の微分積分学と違い、複素関数論では無限大も自然に組み込んで微分や積分を議論できるようになったということのほうが大きいんじゃないかと思います。
複素数は単なる便利な道具だから導入したという理由以上の意義がある
というわけで、上述のように複素数は数学にとって存在することが極めて自然な一つの到達点としての数ということになります。
他の方のブログ記事などを読むと「オイラーの公式が美しい」「物理で計算が楽」という「道具としての複素数」のお話が多く、それはそれで複素数を扱う大きな意義でもあるのですが、数学の発展の歴史から見た複素数の存在意義という記事を見かけなかったので、今回長々と記事を書きました。
複素数を包含する道具としての数の立ち位置
複素数が代数的閉包であることによって、複素数を含んだより広い世界の数への興味はひとまず無くなりました。しかし、複素数を包含して加減乗除などの数学的性質を矛盾なく持った数体系は存在します。
その一つにハミルトンが研究した「四元数」というものがあります。高校数学でも複素数は二次元平面を表すものとして取り上げられますが、四元数は三次元空間を表す数として使われることがあります。方程式の解を探すという興味以外で作られた数ではありますが、道具として使われる場面がある数です。
しかし、三次元空間を記述するための数学の分野、ベクトル解析が発達したことによって、四元数が道具としては使われる場面は圧倒的に少なくなりました。複素数は実数同様、掛け算に順序がなく、$i$ を変数として実数同様の扱いをすればよいだけでしたが、四元数は掛け算の順序によって答えが変わります。道具としても複素数よりも直感的ではありませんでした。また一般の高次元空間を考える際に、それに対応する八元数や十六元数といった元を増やした数体系は複雑さが桁違いに大きくなることで、ベクトル解析を使わずにそれらをわざわざ使う理由も無かったようです。
詳細は省くものの、理論物理学では複素数は当然の文脈で使われています。今後、四元数のような数体系が物理学など「現実世界を扱った学問」で自然に導入されれば活躍の余地もありますが、それがされる場面を見ないところを見ると、現実世界が求める十分な数体系も複素数なんだなと思わせるものがあります。
そもそも自然界に存在する数だから受け入れるという立場について
大昔は虚数以前に、ゼロや負の数や無理数も受け入れられない時代があったのは前述の通りです。でも我々は現代社会で極寒のマイナスの(セルシウス)気温を体験したり、借金で通帳にマイナスが付いたり、黄金比で無理数を普通に扱っています。
高校2年生ごろに習う複素数ですが、虚数単位の「虚」という文字から、ネガティブな印象を抱く高校生も少なからずいるようです。そういう高校生や社会人の「なぜ複素数なんてものを考える必要があるんだ」ということへの回答に、道具として有用な複素数の存在を語っても、上述のような数の体系が受け入れられる歴史の過程のように、心に響く人と響かない人は分かれるんじゃないでしょうか。必要に応じて数を広げて実りある理論を得ていったのが数学の歴史であり、方程式の解を求めるという数学の一つの最重要目標の上では、複素数以上数を広げなくて良い、複素数が数の拡張の一つの重要なゴールなのだというところがとても大事なんじゃないかと。
先ほどのアルキメデス学派のお話を思い出しましょう。アルキメデス学派は線分を極小の点の有限個の集合としていました。
そもそも「自然界に存在する」というのはなんでしょう。
現代物理学では、宇宙は膨張しているものの、大きさは有限であると言っています。有限の空間の中に無限の数のものが果たして存在しているのでしょうか?
大きさが完全に0の素粒子が無限に集まって有限の大きさの粒子や物質を形作っているかということは、現代物理学ではまだ完全に解明できていないようです。現在の素粒子は、今の理論上は大きさがあってもなくても良い。ただ、人間が観察可能な最大の大きさなどはプランク定数という物理定数から求められるといいます。
でも時間は連続的に続いていくでしょという話も、そう簡単な話ではないようです。実際に人間が観察可能な時間の最小の解像度も物理学では分かっていて、それはプランク時間と呼ばれています。プランク時間は約 $5 * 10^{-44}$ 秒という相当な一瞬ですが、これより短い時間が存在するのか、それとも時間は人間が観察できないだけで実は時間は離散的なものなのかはわからないようです。
こう考えると、数直線も時間軸もアルキメデスのような極小の点の有限個の集合であるという見方も、自然界に存在するという視点からはあながち否定できなくなる錯覚を覚えます。せっかく考えた実数という数の集合も、実はほとんどの値が「自然界には存在しない」のでしょうか。
こんなことを言うと「数学の詭弁家」と言われてしまいそうですね。いや、「実際に存在する」とか、そういう価値観で数学の数を論じると、それこそ実数ですら実際に存在するのかわからなくなるという一種の極論です。
ギリシャのプラトンは、地面に描いた三角形に対して、この三角形はゆがんでいるかもしれないけれど、本当の三角形は我々の頭の中にある理想的な三角形を書き写したものに過ぎず、角の和は必ず180度であり、三角形の性質を完全に持っているものだと論じました。彼の哲学理念だったイデア論は、数学のあり方を表しているようです。
私は大学時代、微分積分にまつわる解析学を主に研究していましたが、有限の範囲内で論じた差分公式よりも無限大や無限小を使って論じた微分公式や積分公式のほうがはるかに簡潔かつ理想的に書けることを学び、素数全体の空間であるとか数学的に興味ある構造を明らかにするためには不可欠な理論であることを知りました。古典物理などで扱う物体や重力なども理想的な点物質であったり無限遠を考察したり、無限小や無限大が自然に取り入れられていますが、これも微分積分学の強力さを生かした多くの理論のうちの代表的な一つでしょう。
まとめ
紙に描いた図形や線分は有限の範囲内に有限のインクの点を使って書かれたものですが、それは頭の中の理想では実数の連続性(完備性)を伴った数学的対象です。
方程式の解というものを追求していったことで、数学という学問は複素数という実り豊かのものを手に入れました。今までの狭い数の体系で論じていたことが複素数ではより自然に書けることがわかり、数学は他の学問でも自然現象や社会現象を記述するための有用な道具として使われることになりました。
今や複素数は当たり前のように他の学問に道具として使われますが、そこには代数方程式を追求した数学者達の苦悩や葛藤がありました。そうした人達の努力の末、数学は複素数という一つの理想的な数体系を獲得し、定式化したのでした。